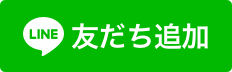エンパス体質について、わかりやすくまとめます【楽に生きるための対策とは】
こんにちは。
エンパスという言葉、最近わりと聞くようになりましたよね。
この記事では、自身がエンパスの立場から
「エンパス体質」というのはどういうことなのか
なるべく分かりやすくまとめています。
更には、エンパスという体質とうまく付き合って、
楽に生きるヒントについても
生きづらさを克服してきた立場から書いています。
もくじ
エンパス体質の特徴と対策について
エンパス体質にいて
エンパスさんの特徴とは
いま日本では5人に一人がエンパス体質とも言われていて、
サイコパスという言葉の対義語として使われています。
エンパスの特徴を一言で表すと、
人の気持ちや感覚が言葉で聞くことなくとも
感覚でわかるということです。
人の気持ちが分かるという面では
スピリチュアルな能力ともいえると思います。
HSPとの違いって?
「HSP」という言葉も、よく聞くようになりましたよね。
では「HSPとエンパスってどう違うのだろう」と考えたときに
HSPという大きなくくりの中に
エンパスが入っているという感じです。
HSPという特性を持っていて、
さらに人の感情に敏感な方が
エンパスと言ってもいいと思います。
HSPに関しては、人の感情には敏感でなくとも
音や光に対してなど五感が敏感な方のことも指します。
エンパスゆえの悩みとは
エンパスの方は人の感情に敏感ゆえ
関わる人次第で感情が左右されやすいです。
それゆえに生きずらさを抱えてしまうこともあります。
なので、人の影響を受けない自分だけの時間を持つと
元気を取り戻しやすいです。
エンパス体質で人に影響されやすくてつらい、
という方へは、ほんの少しの時間でもいいので
近所の公園に行ってみるなどもおすすめです^^
生きづらさを解消するためには
エンパスゆえの生きづらさ
人の感情が分かるということは
自然と自分より人を優先することにつながりやすいです。
また、エンパスさんはサイコパスや
人のエネルギーを吸い取る方につかまりやすいため
「気」が枯渇しがちです。
人は気が巡ることで生きているので
気が枯渇するということは生きづらさにつながりやすいんですね。
ではどうしたらいいかについても
以下に書いてゆきたいと思います。
自分だけの時間を持つ
先ほども少し書きましたが、
一日にほんの10分からでもいいので
自分だけの時間をもつことがおすすめです。
例えば小さいお子さんの子育て中であれば
ご自身の時間を持つことはなかなか難しいとは思うのですが
お子さんのお昼寝中や寝かしつけの後など。
お勤めされているかたであれば、
お昼休みのお食事後など。
瞑想ができればいいのですが、エンパスさんは頭脳優位で
ご自身を守っ生きてきている場合も多いので
最初は難しいかもしれません。
実は、わたしもいまだに瞑想は苦手です…^^;
瞑想が難しいという場合は、好きな音楽を聴く、本を読む
マンガを読む、などでも、じゅうぶんに
ご自身と向き合える時間となります。
よろしければぜひ、試されてみてくださいね^^
病気ではないと個人的には思う理由
いま、発達障害やADHDなど
精神的な疾患の名前って沢山ありますよね。
心配になってチェックリストを見に行くと
これもあてはまっている、あれもあてはまっていると
余計に不安になることがあるかと思います。
特にエンパスさんは、そういったテストの
チェックリストでは
どれかに当てはまる場合が多いかと思います。
ある程度それぞれの特徴があると思うので
把握して対策する上では必要なことでもあるとは感じます。
そういった特徴を持ったお子さんが
より適切な教育を受けられたりという側面もありますよね。
一方で、すこしでも精神科疾患の特徴があるというだけで
そこまでではないのに薬を飲むことになると
感覚を感じづらくなります。
すると、本来はとても素晴らしいことである
共感力や繊細な感性をつぶしてしまうので
それはもったいないと思っています。
感覚を感じても恐くない環境を作ることが、大切
では、エンパス体質の方が現代社会で
自分の感覚を大切に生きるためには
どうしたらいいんだろうという事なのですが。
感覚を感じても恐くない
のびのびと感覚を感じられる時間や空間を
増やすことだと思っています。
個人的には、使う言葉から変える方法を
おすすめめしています。
そちらは無料のステップメールでまとめていて
こちらで詳細をご覧いただけます。
型にとらわれないことが大切
この記事の最後に一つお伝えしたいのは
「型にとらわれないことが大切だよ」ということです。
いまの世の中、型に当てはめる言葉って本当にあふれていて
何かに属していることは安心感につながるとは思います。
でも一方で「〇〇のわたし」と自分をくくることは
現実世界での自分の範囲を狭めることにつながりやすいです。
「のびのび楽に、楽しく、自分の使命を生きたい!」
と思ったら「〇〇のわたし」という
この「〇〇」を取り払ってみるのも大切です。
ぜひ試してみてくださいね^^
こころの整えについて深いお話は、
LINE公式でもお伝えしています。
よろしければ以下よりお気軽にご登録お待ちしております^^